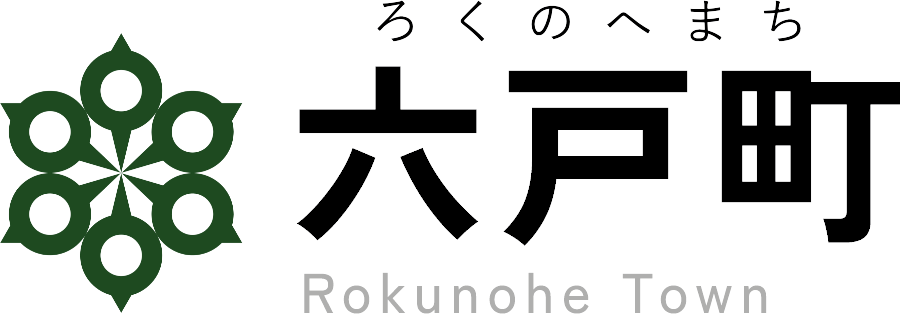記事番号: 1-1782
公開日 2022年04月11日
文化財は、文化財保護法や六戸町文化財保護条例等に基づき、指定、登録、選定することにより保護されています。
六戸町の文化財は、有形文化財、無形文化財、民俗資料、史跡天然記念物に分類され指定されています。
有形文化財
学秀作大日如来像、学秀作七菩薩像
[六戸町文化財指定:平成13年10月14日]
鶴喰地区にある月窓寺境内に有形文化財の指定を受けている学秀作の大日如来像、七菩薩像が安置されています。
旧苫米地家住宅
[六戸町文化財指定:平成4年11月30日]
六戸町において、奥入瀬川流域に現存する家屋のうちでは最古と思われるのが、柳町の苫米地勲氏の住宅であり、いまは、国道45号線沿いにある道の駅「ろくのへ」の隣に平成17年3月に移築し、一般開放しています。
苫米地家の由緒やこの家屋の建築年代を示す資料などは一切残されていませんが、上北地方の民家の建築手法の進展状況から比較してみると、おそらく江戸時代後半には建てられたものと推測されています。苫米地家住宅の特徴の一つとして、「しきだい(式台)」と呼ばれる施設が設けられており、当時は武士階級の住宅に限られた出入口(建物正面左側)であったとされ、身分や家の格式を表現する施設であったとみられます。
 |
苫米地家住宅の茅葺屋根の形は「寄せ棟」造りで、屋根の中央には「煙出し」もみえます。そして桁行方向(正面)11間、梁間(奥行)5間の建て坪約55坪(この場合、1坪は3.3平方メートルより若干大きい)に及ぶ「すごや(直家)」形式です。その他の特徴としては、内壁に土壁を塗った「クモ壁」という珍しい工法をみることができます。また、梁や指物には今でも釿削りのこん跡が認められ、その歴史の古さを物語っています。(六戸町史上巻抜粋)
無形文化財
鶴喰鶏舞
[六戸町文化財指定:昭和55年2月18日]
寛永年間、代官として居を構えた存応が惨殺され、霊を供養するために月窓寺が建てられ鶏舞が踊られたといわれています。
鶏舞は、踊り念仏の一種で五穀豊穣・無病息災・家内安全を祈願する踊りです。踊り念仏とは、念仏を唱えながら先祖の精霊を供養する踊りですが、鶏舞はそれに加え、集落の繁栄と家内の福を祈る祝いの舞として継承されています。
 |
鶴喰鶏舞
折茂今熊神楽
[六戸町文化財指定:昭和55年2月18日]
早池峰系の岳神楽を祖とする今熊神楽は早池峰から伝わったといわれています。
歯打ちをする熊野神楽の流れを汲む山伏神楽で、演目として「権現舞・花舞・鞍馬・山の神・三番叟・新玉句・祝いうた」等があります。
旧正月には、地域の家々を家内安全・五穀豊穣・無病息災を祈り、門打ちをして回ります。
 |
折茂今熊神楽
上吉田南部駒舞
[六戸町文化財指定:昭和55年2月18日]
駒舞は、軍馬育成のため野に放たれ半ば野生化した馬を、盛装した騎馬武者が捕らえる、いわゆる御野馬捕りを舞踊化したものであるといわれています。また、捕獲した馬を獣から守り、走逸を防ぐための太刀・薙刀等を用いた附舞、七つの道具があります。
主に神仏を祈願供養するための舞であるため、お盆には地域の人たちに披露されています。
 |
上吉田南部駒舞
上吉田大黒舞
大黒舞は、豊作を祈願し、豊年に感謝する芸能で、農家の最大の祈りと感謝の意を表しています。小正月や季節の折には、たっつけ袴にはっぴを着て、頭には大黒頭巾をかぶり、手に小槌と日の丸の扇子を持った大黒天の姿で家々を回り、祝儀歌に合わせ家内安全・商売繁盛を祈願する歌舞を演じています。
 |
上吉田大黒舞
天然記念物
久乃助のイチイ
[六戸町文化財指定:平成4年11月30日]
この地方でオンコ(アイヌ語)ともいわれ、この地方の生活と風土に密着した樹木でもあります。周辺市町村を含めても最古のものと考えられています。
- 推定樹齢:500年。
- 目通幹回り:4m30㎝。
 |
久乃助のイチイ
今熊神社の杉
[六戸町文化財指定:平成4年11月30日]
折茂集落から1㎞ほど北西の小高い丘に、六戸町で最も古い神社といわれる今熊保食神社が鎮座しています。神社の左後方に六戸町で指定している杉が植栽されています。
- 推定樹齢:400年。
- 目通幹回り:3m95㎝。
 |
今熊神社の境内
鶴喰若宮八幡宮のサワラ、カツラ、銀杏
[六戸町文化財指定:平成4年11月30日]
鶴喰集落南方の高台、鶴喰館先端付近に東方を向いて鶴喰若宮八幡宮が鎮座しています。参道にはサワラ・桂・銀杏の古木を御神木として注連縄が張られ、この3本の御神木を六戸町で指定をしています。
|
|
||
 |
 |
 |
| 【サワラ】 推定樹齢:400年 目通幹回り:3m30cm |
【桂】 推定樹齢:400年 目通幹回り:6m95cm |
【銀杏】 推定樹齢:400年 目通幹回り:4m55cm |