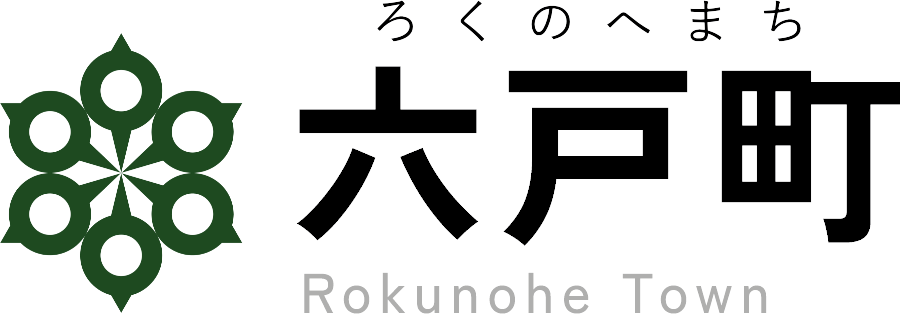記事番号: 1-2041
公開日 2025年08月28日
介護保険のサービスを利用するためには、町へ申請が必要です。申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定されたときにサービスを利用することができます。
申請は本人または家族が申請するか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業所などに申請を代行してもらうこともできます。
原則として費用の1割を負担しますが、一定以上の所得のある方は2〜3割負担となる場合があります。
申請
サービスが必要となったら、地域包括支援センターの窓口で「要介護認定」の申請をしましょう。申請は本人または家族が申請するか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業所などに申請を代行してもらうこともできます。
- 申請に必要なもの
- 介護保険 要介護・要支援認定 申請書
- 介護保険被保険者証(紛失の場合、再交付申請書を添付)
※注 第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険加入者)は、医療保険被保険者証のコピーを添付
要介護認定の審査・判定
- 認定調査/主治医意見書
- 認定調査…町職員や町から委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)などが訪問し、心身の状況など訪問調査票(全国共通)に基づき、本人や家族から聞き取り調査を行います。
- 主治医意見書…本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
- 審査・判定
- 認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家が審査・判定します。
認定結果の通知
判定にもとづき、町が要介護状態区分を認定し、通知します。
原則として申請から30日以内に、町から認定結果通知書と、認定結果が記載された保険証が郵送されます。
| 要介護状態区分 | 利用できるサービス |
|---|---|
| 要介護5 | 介護保険の介護サービス 日常生活で介助を必要とする度合いの高い人で、 生活の維持・改善を図るためのさまざまな介護サービスを利用できます。 |
| 要介護4 | |
| 要介護3 | |
| 要介護2 | |
| 要介護1 | |
| 要支援2 | 介護保険の介護予防サービス 要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが 受けるサービスです。 |
| 要支援1 | |
| 非該当 | 町が行う介護予防事業 介護保険のサービスの対象者にはなりませんが、 生活機能の向上が必要と判定された人などが利用できます。 |
ケアプランの作成
- 要介護1〜5と認定された人
在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス(ケアプラン)を作成してもらいます。
- 要支援1・2と認定された人
地域包括支援センターで保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
サービスの利用
サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。原則として費用の1割を負担しますが、一定以上の所得のある方は2〜3割負担となる場合があります。
ダウンロード
よくわかる介護保険「申請からサービスの利用まで」- 申請書等様式
過誤申立依頼書(様式)[XLSX:15.3KB]
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定有効期間延長申出書 (PDF文書/77KB)
(PDF文書/77KB)
介護保険被保険者証等再交付申請書 (PDF文書/79KB)
(PDF文書/79KB)
介護保険要介護・要支援認定取消申請 書(PDF文書/71KB)
書(PDF文書/71KB)
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (PDF文書/93KB)
(PDF文書/93KB)
(介護予防)居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (PDF文書/90KB)
(PDF文書/90KB)
情報提供依頼書 (PDF文書/57KB)
(PDF文書/57KB)
情報提供依頼書(複数依頼用) (PDF文書/28KB)
(PDF文書/28KB)
介護保険関係書類送付先変更申請書 (PDF文書/66KB)
(PDF文書/66KB)
介護保険住所地特例対象施設入退所連絡票 (PDF文書/64KB)
(PDF文書/64KB)
介護保険施設入所・退所連絡票 (PDF文書/59KB)
(PDF文書/59KB)
グループホーム入退居者連絡票 (PDF文書/40KB)
(PDF文書/40KB)
介護保険負担限度額認定申請書 (PDF文書/134KB)
(PDF文書/134KB)
介護保険負担限度額認定同意書 (PDF文書/62KB)
(PDF文書/62KB)
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する届出書(様式1)[DOCX:16.7KB]
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する届出書(様式2)[DOCX:17.3KB]
医学的所見(参考様式)[DOCX:14KB]
医師の医学的所見に係る確認書(参考様式)[DOCX:13.9KB]
福祉用具購入理由書[XLSX:37.1KB]
介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書[DOCX:14.8KB]
介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書[DOC:45KB]
介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(付票:事前審査申請書)[DOC:32.5KB]
住宅改修の承諾書[DOC:33KB]
住宅改修が必要な理由書P1[XLS:40KB]
住宅改修が必要な理由書P2[XLS:40.5KB]
この記事に関するお問い合わせ
介護高齢課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字後田19-1
TEL:0176-27-6688
FAX:0176-55-3033